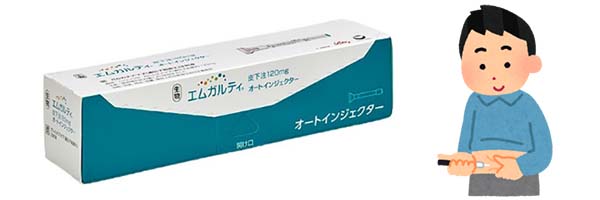頭痛は病気です。市販薬を飲みすぎていませんか?
頭痛はただの不快感ではなく、病気の一種です。もし、頻繁に頭痛が起きていたり、市販薬を何度も飲んでいる場合、適切な対処が必要です。市販薬を多く使うことは、一時的に痛みを和らげるかもしれませんが、症状が悪化したり、薬の効果が薄れることもあります。
迷ったら、ぜひご受診ください。
脳神経外科での診療対象
中学生以下のお子様
過去に頭の手術、事故で頭をぶつけた経験、最近、頭をぶつけた方は脳神経外科での受診をお願いします。そちらから適切な病院を紹介してもらうことをお勧めします。当院から脳神経外科に紹介することがあります。当院での受診を希望される場合は、紹介状をお持ちください。
頭痛専門医とは
頭痛は多くの方が経験する症状ですが、なかには専門的な診断や治療が必要な場合もあります。
頭痛専門医は、日本頭痛学会が認定する、頭痛診療に特化した医師です。
片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などの慢性頭痛から、くも膜下出血などの重大な頭痛まで、専門的な知識と経験をもとに診断・治療を行います。
頭痛専門医になるには
頭痛専門医になるためには、以下の条件が必要です
- 医師免許を持ち、一定年数の臨床経験があること
- 日本頭痛学会に所属し、頭痛診療に関する知識と技術を深めていること
- 学会が定める研修・講習を修了し、筆記試験に合格していること
- 認定後も定期的に更新のための研修を受けていること
このように、専門的な研修と認定を受けた医師が「頭痛専門医」として活動しています。
診療の流れ
- 医療面接(問診)
- 一般内科検査
- 神経診察
- 病巣診断
- 治療
主な検査
MRI・CT検査
1次性頭痛か2次性頭痛の判断
近隣の施設をご案内します。
当日検査、当日結果説明も予約状況により可能です。
採血検査
お薬による治療を始める前後には、肝臓や腎臓の働きなどを血液検査で確認することが大切です。これは、副作用の予防や、薬の影響を適切に評価するために行います。
頭痛と脂質の関係
頭痛の原因はさまざまですが、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が高いと、血管の働きに影響し、頭痛が起こりやすくなる場合があります。
採血で脂質を調べることで、生活習慣や血管の健康状態を把握し、必要に応じて対策を検討できます。
神経学的検査
脳、脊髄、神経、筋肉の機能を評価する検査です。頭痛、めまい、しびれなどの症状がある患者に対して、意識状態、言語、脳神経、運動機能、感覚機能、反射、協調運動、歩行などを総合的に評価します。
どのような時に受診すれば良いのでしょうか?
頭痛があった場合、もちろん受診を検討するべきですが、それ以外のタイミングでも受診が有効な場合があります。以下のような状況では、早めに専門医に相談することをお勧めします。
1. 頭痛がひどくなる前に受診する
- 頭痛が実際に起きていない時でも受診は可能です。むしろ、痛みがない時の方が、医師が冷静に診断を行いやすく、適切な治療方法を提案しやすい場合もあります。
2. 頭痛が日常生活に支障をきたす場合
- 頭痛がひどくなることで、食事や旅行、仕事、友人との約束など、普段の生活に支障をきたすことが多い場合。
- 「また頭痛が起きるかも」と思って、予定をキャンセルしてしまうことが増えてきた場合。
3. 市販薬が効かない時
- 市販薬を飲んでも、痛みが改善しない場合や、痛みが強くなっていく場合は、早めに医師に相談しましょう。過度に市販薬を使用すると、薬物乱用頭痛を引き起こす可能性もあります。
4. 頭痛の頻度が増えた場合
- 「最近、頭痛が以前より増えてきた」と感じている方は、頭痛の原因を特定するために受診を検討してください。頭痛のタイプや原因によっては、早期の治療が症状を軽減することがあります。
5. 痛みの性質が変わった時
- 以前と比べて頭痛の痛みが変わったり、新たな症状(吐き気、視覚異常、めまいなど)が伴う場合も受診のサインです。これらの症状が出ると、より深刻な病気が隠れていることもあるため、慎重に診察を受けることが大切です。
受診のタイミングは、頭痛が起きていない時でも構いません。
実際に頭痛が起きていないタイミングで受診することには、大きな利点があります。痛みがない時にこそ、医師は客観的に症状を分析し、適切な治療法や予防方法を見つけることができます。
特に、頭痛が起きる前に予防策を講じることができれば、今後の頭痛を減らすための準備が整います。
頭痛は放置せず、早期の対処が重要です。もし「自分の頭痛は大丈夫かな?」と感じたら、迷わず受診をお勧めします。頭痛の再発を予防するために、専門医と一緒に原因を探し、効果的な治療を始めましょう。
頭痛の種類
一次性頭痛
原因となる疾患や脳MRI検査などで異常がなく頭痛自体が病気である。
片頭痛・緊張型頭痛頭痛・群発性頭痛など
二次性頭痛
命に関わることもある危険な頭痛(二次性頭痛)です。
くも膜下出血・脳出血といった脳卒中・脳腫瘍・髄膜炎など
頭痛ダイアリー
ご自身の頭痛の様子を毎日記録していただくノートやアプリのことです。
頭痛の頻度・痛みの強さ・部位・持続時間・誘因(きっかけ)・服用した薬などを記録することで、頭痛の種類(片頭痛・群発頭痛・緊張型頭痛など)や、生活習慣との関係を客観的に把握することができます。
この記録は、以下の目的で活用されます
- 痛みのパターンや変化の把握
- 薬の効果や副作用の確認
- 予防薬や治療方針の調整
- 薬物の使いすぎ(薬物乱用頭痛)の予防
- 日々の記録が、治療をスムーズに進める大きな手助けとなります。
紙の記録用紙をご希望の方には、診察時にお渡しいたします。スマートフォンで記録したい方には、便利な無料アプリもご紹介しております。
頭痛の治療方法
頭痛の治療は、原因や症状に応じて異なりますが、基本的には以下の方法が一般的です。
1. 痛みを和らげる薬
市販薬: 頭痛の痛みを和らげるための薬(例:アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)が使われます。痛みがひどくならないうちに服用すると効果的です。
処方薬: 片頭痛や緊張型頭痛の場合、医師が処方する薬を使うことがあります。片頭痛にはトリプタン系薬剤が有名です。
2. ライフスタイルの改善
睡眠: しっかりとした睡眠を取ることが頭痛の予防につながります。
ストレス管理: リラックスできる時間を作る、運動や趣味を楽しむことが有効です。
食生活: 食事のバランスを保つことも大切です。特に、片頭痛の場合、特定の食べ物(チョコレート、チーズなど)が誘因になることがあるため、注意が必要です。
3. 物理療法
温湿布や冷湿布: 頭痛が起きたときに冷やしたり温めたりすることで痛みが和らぐことがあります。
マッサージや整体: 首や肩のこりが原因の頭痛には、マッサージや整体も効果的なことがあります。
頭痛の予防法
頭痛を繰り返さないようにするためには、生活習慣の改善とともに、予防薬や予防注射を使うことも有効です。以下の方法で頭痛の予防が可能です。
1. ストレスの管理
- ストレスは頭痛の引き金になりやすいため、リラックスする時間を取ることが大切です。ヨガや瞑想、趣味を楽しむ時間を持つことで、ストレスが軽減し、頭痛の予防になります。
2. 規則正しい生活
- 睡眠: 毎日一定の時間に寝て、十分な睡眠を取ることが予防に繋がります。睡眠不足は頭痛の原因になりやすいので、規則正しい睡眠を心がけましょう。
- 食事: 食事の時間を決めて、栄養バランスを意識した食事をとることが大切です。特に、低血糖や脱水が引き起こす頭痛を防ぐために、水分補給も忘れずに。
3. 体調管理
- 運動: 体を動かすことで血行が促進され、頭痛を予防する効果があります。特に軽いジョギングやウォーキングなどの有酸素運動がオススメです。
- 姿勢改善: 長時間同じ姿勢でいることは、肩こりや首の痛みを引き起こし、それが頭痛につながることがあります。定期的に姿勢をチェックし、休憩を取ることが重要です。
4. トリガーを避ける
- 特定の食べ物や環境が頭痛の引き金になることがあります。例えば、チョコレートやチーズ、アルコール、強い光、騒音などがトリガーになることがあるので、これらを避けることで頭痛を予防できます。
予防薬と予防注射
頭痛の予防には、薬物療法が効果的な場合もあります。特に、頻繁に頭痛が起きる場合や、薬を使っても頭痛が改善しない場合には、医師と相談して予防薬や予防注射を使用することがあります。
1. 予防薬
予防薬は、頭痛の発作を起こさないように、または発作の回数や強さを減らすために使われます。頭痛が頻繁に起こる人や、片頭痛の症状が重い人には特に効果的です。
- ベータ遮断薬(例:プロプラノロール)
血管の拡張を抑える作用があり、片頭痛の予防に用いられます。
- 抗うつ薬(例:アミトリプチリン)
片頭痛の予防に使われることがあります。特に、睡眠やストレス管理が重要な場合に役立ちます。
- 抗てんかん薬(例:バルプロ酸)
頭痛の発作を防ぐ効果があります。特に片頭痛や群発頭痛に使用されます。
- カルシウム拮抗薬(例:ベラパミル)
血管の収縮を抑え、片頭痛の予防に使われることがあります。
2. 予防注射
頭痛が非常に頻繁に、または重度の場合には、予防注射を検討することもあります。特に、片頭痛に対しては最近新しい予防注射が効果的であるとされています。
CGRP関連抗体注射(エムガルディ・アイモビーグ・アジョビ)
CGRP関連抗体注射(エムガルディ・アイモビーグ・アジョビ)は、片頭痛の発作を予防する新しい治療法です。
CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)は片頭痛発作の引き金となる神経ペプチドで、その働きを阻害することで発作を抑えます。
治療は月1回または3か月に1回の皮下注射で行い、長期的な効果と良好な忍容性が報告されています。
従来の予防薬が効果不十分な方や副作用で継続が難しい方にとって、有効な選択肢となります。
その他の予防策
- マインドフルネスやリラックス法: ストレスを減らすための方法として、深呼吸やリラクゼーション技術を取り入れることが予防に役立ちます。
- 定期的な医師の診察: 頭痛が頻繁に起こる場合や、薬が効かない場合には、医師と相談して適切な予防策を講じることが重要です。
まとめ
頭痛の予防には、日常生活の改善に加えて、必要に応じて予防薬や予防注射を活用することが重要です。自分に合った予防方法を見つけるためにも、専門医と相談しながら治療を進めていきましょう。日々の生活習慣を見直し、適切な治療を受けることで、頭痛を減らし、より快適な生活を送ることができます。
注射による片頭痛予防療法(CGRP関連薬治療)
近年注目されている新しい予防治療法
片頭痛は、日常生活に大きな支障をきたす慢性疾患です。従来の内服薬による予防療法に加えて、CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)という神経伝達物質を標的とした注射製剤(抗CGRP抗体)が、近年新たな治療選択肢として登場しました。
この治療法は、月に1回〜3ヶ月に1回の皮下注射で、片頭痛発作の頻度や強度を抑えることが可能です。
対象となる方
- 月に片頭痛が4回以上ある方
- これまでの内服薬による予防治療で効果が不十分だった方
- 副作用や服薬の継続が難しかった方
- 生活の質(QOL)を大きく損なっている方
※医師の診断により適応が判断されます。
エムガルディ
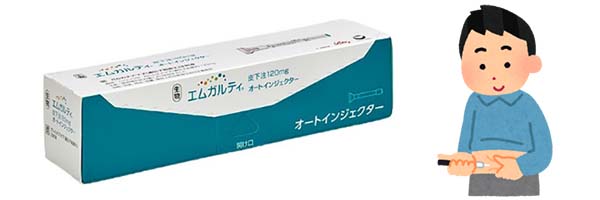
- 投与方法:初回2本、以降は1カ月間隔で1本注射します。
アイモビーグ

アジョビ

- 投与方法:初回1本、1カ月間隔で1本注射します。または、初回3本、3カ月間隔で3本注射します。
 頭痛・めまい・しびれの専門医による診療
頭痛・めまい・しびれの専門医による診療